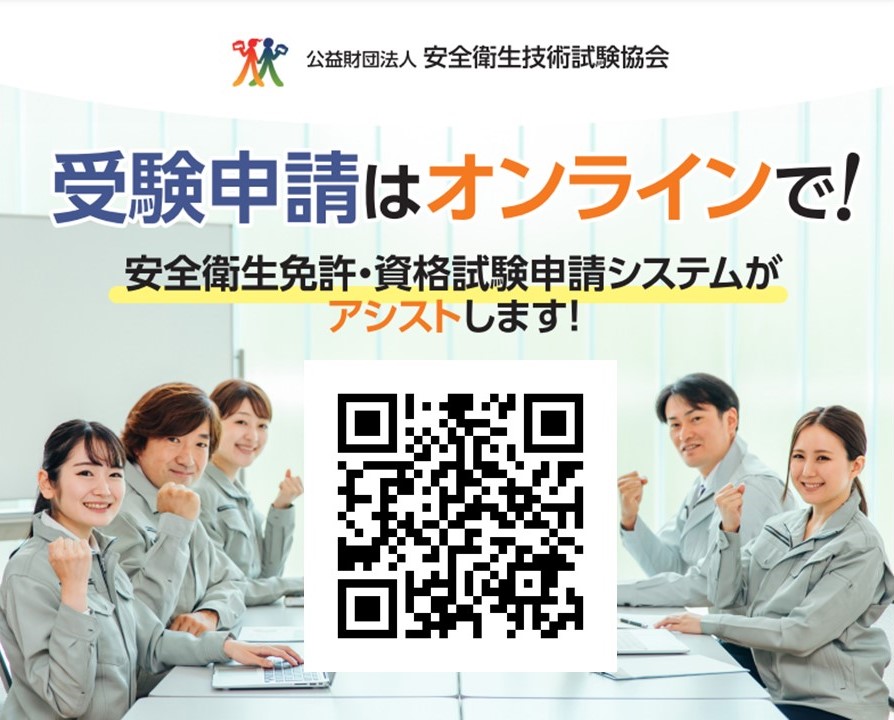受講キャンセルについて
申込み後の取消しは、締切日までにご連絡のあった場合に限り受講料をお返し致します。
申込締切日後の受講キャンセルにつきましては、いかなる理由がありましても受講料の返金は致しませんので、あらかじめご了承下さい。
講習会の出張講習、単独講習
各事業場様への出張講習、単独講習も可能ですので、ご相談下さい。
(1)対応の講習会
・新入者安全衛生講習 ・職長教育 ・KYTリーダー(基礎)研修会 ・リスクアセスメント教育 等
(2)対応地域
弘前市近郊
(3)日程
ご相談下さい。
(4)受講者の人数について
各科目、原則20名様以上。 少数の場合、ご相談ください。
(5)講習会場等
お客様ご指定の場所で実施いたします。
会場が見つからない場合は当協会へご相談下さい。
(6)講習料金 当協会が通常実施している料金です。
講習料金(受講料+テキスト代)×人数となります。
受講者が少数の場合は別途、相談となります。
(7)修了証の交付
即日、修了証の交付が可能です。
技能講習
- 玉掛け技能講習 (青森県労働局長 登録教習機関 登録番号 第92号)
- 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくは
デリックの玉掛け業務を行うことができます。
- フォークリフト運転技能講習 (青森県労働局長 登録教習機関 登録番号 第93号)
- 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務を行うことができます。
- 小型移動式クレーン運転技能講習 (青森県労働局長 登録教習機関 登録番号 第95号)
- つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーン運転業務を行うことができます。
- ガス溶接技能講習 (青森県労働局長 登録教習機関 登録番号 第121号)
- 可燃性ガス(アセチレン等)及び酸素を用いて行う金属の溶接、
溶断又は加熱の業務を行うことができます。
特別教育
- テールゲートリフター特別教育
- 荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、特別教育を実施する必要があります。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含まれます。
※改正内容等の詳細は 厚生労働省の資料(PDF) でご確認下さい。
- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育
- 事業者は作業者に対し、石綿(アスベスト)等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業に労働者をつかせるときは、石綿(アスベスト)によるばく露の危険性があることから、特別教育(安衛則第36条第1項第37号)を行わなければなりません。
- 動力巻上機運転業務
- ウインチを使用する作業は、不適切な取扱いが原因で災害が起こることが多い危険な業務であるため、事業者は、標記業務に従事する労働者に対して、労働安全衛生法第59条第3項、同規則第36条の規定により、危険業務従事者に対する安全のための特別教育(教育規程に基づいた修了者)実施が義務付けられております。
- クレーン運転業務
- つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
- 高所作業車運転業務
- 高所作業車とは、高所における作業を行なうために人が乗る作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。労働安全衛生規則第36条第10号の5により、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車は、運転特別教育を修了した者でなければ運転できません。
- 低圧電気取扱業務
- 労働安全衛生法では低圧(直流750V以下、交流600V以下)の電気取扱い作業を行う者に対して、安全に関する特別教育を行った者でなければ就業させることが出来ないことになっております。
低圧の配線の接続作業等、感電の危険のある作業に必要な資格です。
電気事業法による電気主任技術者や電気工事士の資格を取得していても、労働安全衛生法で定める特別教育の修了が必要です。
実技は1時間(開閉器の操作の業務のみ)の教育を実施しております。
- 粉じん作業
- 事業者は、粉じん作業に従事する労働者に対して、労働安全衛生法第59条3項、同規則36条の規定により、危険業務従事者に対する安全のための特別教育(教育規程に基づいた修了者)実施が義務付けられております。
- 自由研削といし取替等業務
- 事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
安全衛生教育
- 新入者安全衛生教育
- 事業場で新たに労働者を雇い入れた場合には、当該労働者に労働安全衛生法の定めにより、
その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならないことになっております。(労働安全衛生法第59条第1項)
- 携帯用丸のこ盤取扱作業従事者安全教育
- 携帯用丸のこ盤は、その携帯性と使用しやすさから建設業をはじめ、様々な業種
において広く使用されている工具です。のこ歯は、電気によって高速回転させる工具であるため、災害が後を絶ちません。このため、厚生労働省では、上記業務に従事する労働者に対し、安全教育の実施及び実施要領を定めております。(平成22年7月14日付 基安発0714第1号通達)当協会では、この実施要領に基づく教育を実施致します。
- 安全衛生推進者養成講習 (青森県労働局長 登録教習機関 登録番号 第3号)
- 安全衛生推進者選任対象事業場
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、次に揚げる業種が対象となります。
(労働安全衛生法第12条の2により、選任が義務づけられています。)
※ 支店、営業所、工場、建設現場等の事業場単位での選任が必要です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、燃料小売業、旅館業、家具・建具・じゅう器等卸売業、家具・建具・じゅう器等小売業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
※上記以外の業種の事業場については、「衛生推進者」の選任が必要となります。
なお、安衛法施行令第2条第3号に掲げる事業場(小売業、社会福祉施設、飲食店)で、常時10人以上の労働者を使用する事業場にあっては「安全推進者」を配置することが望ましいとするガイドラインが平成26年3月に策定されましたので、「安全推進者」の資格要件であります本講習を受講されることをおすすめいたします。
- 職長・安全衛生責任者教育
- 事業者は、職場の職長等の第一線監督者に新たに就く者に対して、必要な教育を行わなければならないとなっております。
職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています。(労働安全衛生法第60条)。職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長などさまざまな名称で呼ばれています。名称はともかく、仕事を行う上で、現場で指揮、命令する人が職長です。
◆ 職長等の教育を行うべき業種(労働安全衛生法施行令第19条)
1.建 設 業
2.製 造 業(但し、食料品、たばこ、繊維工業、新聞、出版、製本及び印刷物加工を除く)
※令和5年4月1日から対象業種が拡大され「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷 物加工業」の2業種が新たに加わり義務化になります。
↓
職長等に対する安全衛生教育を実施しましょう(弘前労働基準監督署からのお知らせ)
3.電 気 業
4.ガ ス 業
5.自動車修理業
6.機械修理業
◆安全衛生責任者教育を行うべき業種
1.建 設 業 2.造 船 業
労働安全衛生法第16条では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(元方事業者)以外の請負事業者(関係請負事業者)においては、安全衛生責任者を選任し、その者が統括安全衛生責任者と連絡をとりながら、労働災害防止の措置をとるように定めております。
- 刈払機取扱作業従事者安全衛生教育
- 刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事するものに対し、必要な知識等を付与する目的の安全衛生教育です。
- 安全管理者選任時研修
- 常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場は安全監理者を選定し監督署長への届け出が必要です。
安全管理者選任時研修はどなたでも受講可能ですが、
安全管理者の選任には厚生労働大臣の定める研修(安全管理者選任時研修)を修了し、一定の産業安全の実務経験が必要です。安全管理者について(厚生労働省)
このことにより、安全管理者の転勤、異動等により、安全管理者が未選任の状態とならないよ うに、本研修修了者を複数人確保しておくことが望まれます。
- KYTリーダー(基礎)研修会
- KYT(危険予知訓練)とは、職場や作業の中に潜む危険要因を発見・把握・解決していく手法の一つで、ヒューマンエラー事故防止に有効な手段となっています。
この研修会では、危険感受性を高め、KYT(危険予知訓練)手法を基礎から研修し、ゼロ災害・ゼロ疾病を目標に、職場や作業に潜む危険の芽をあらかじめ自主的に取り除くとともに、前向きで参加的、創造的な職場風土づくりをめざす実践活動に貢献するものです。
事業場内でKY活動をより確実に普及浸透させるためには、複数名の参加が効果的です。
- リスクアセスメント教育
- 平成18年4月1日施行労働安全衛生法の改正により、危険性または有害性等の調査及び低減措置(リスクアセスメント)を事業者が実施するように努めなければならないと義務づけられました。当協会では、事業場の安全衛生の水準を図ることを目的にリスクアセスメントの実務を担当する方々を対象に、リスクアセスメントの基本から運用等手法の演習を含めた研修を開催いたします。
- 振動工具取扱作業者教育
- 平成21年7月「チェーンソー以外の振動工具取扱業務に係る振動障害予防対策指針が改正」され、振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱により、振動工具のための安全衛生教育を実施します。
免許申請資格講習
- ボイラー実技講習 (青森労働局長 登録講習機関 登録番号 第2号)
- ボイラー実技講習は、その受講・修了が免許交付要件の一つとして位置づけられる講習です。従前どおり、免許試験の受験前に受講するほか、免許試験に合格した後に受講することもできます。 ボイラー取扱などの経験を得る機会のない方は、ボイラー実技講習を受講・修了することにより、二級ボイラー技士免許試験に合格すれば、免許を取得することができます。
受験準備講習
- 衛生管理者受験
- 衛生管理者の試験を受験される方を対象に、講習会を開催致します。